児童虐待予防教育について
児童虐待予防教育とは?
子ども自身で、自分の「体」「心」「命」そして自分の「未来」を守ることができるように、『生きる力』を引き上げる教育です。
予防教育の必要性
現代社会において、児童虐待は深刻な社会問題として認識されています。痛ましい事件が後を絶たず、その背景には、孤立した育児環境や親自身の心の傷など、様々な要因が複雑に絡み合っています。このような現状を打破し、すべての子どもたちが安全で健やかに成長できる社会を築くためには、児童虐待が起きてから対処するだけでなく、その発生を未然に防ぐ「予防教育」が不可欠なのでです。
①に、予防教育は、虐待の早期発見に役立ちます。
虐待を受けている子どもは、しばしば助けを求める声を上げることができません。また、虐待を行っている親自身も、それが問題行動であると認識できていないケースがあります。
予防教育は、子ども自身に「自分は大切にされるべき存在である」という自己肯定感を育むとともに、「危険な状況」を認識し、誰かに助けを求める術を教えます。
同時に、周囲の大人たちに対しても、虐待のサインや、困っている親子にどう関わるべきかといった知識を提供することで、地域全体で見守る目を養うことができます。
②に、予防教育は、虐待の連鎖を断ち切るために重要です。
虐待をしてしまう親の中には、自身が幼少期に虐待を経験している人が少なくありません。彼らは、適切な子育ての方法や、感情のコントロールの仕方を学ぶ機会がなかったために、無意識のうちに負の連鎖を繰り返してしまうことがあります。
予防教育を受けた子どもは、大人になって親になったとき、健全な親子関係を築いたり、子どもをリスクから守ったりすることに意識が向きやすくなります。その結果、子どもが健やかに成長できる未来を築くことができます。
③に、予防教育は、社会全体の子育て支援意識を高めます。
児童虐待は、特定の家庭だけの問題ではなく、社会全体で取り組むべき課題です。学校、地域、行政、NPOなど、様々な機関が連携し、子育てに悩む親が気軽に相談できる環境や、孤立を防ぐためのコミュニティを築く必要があります。予防教育は、こうした社会的支援の重要性を広く人々に伝え、誰もが子育てを支える一員であるという意識を醸成する役割を担います。これにより、「困った時は頼っていいんだ」という安心感が生まれ、孤立による虐待のリスクを減らすことにつながります。
「児童虐待」の一般的なイメージについて
児童虐待という言葉を聞くと、多くの人がテレビのニュースや新聞で報道される痛ましい事件を思い浮かべるでしょう。
幼い命が失われたり、心身に深い傷を負わされたりする、見るに堪えない出来事。そうした悲劇的な事態が、児童虐待の一般的なイメージとして定着しているように思います。
しかし、同時に多くの人は「それは遠い世界の出来事だ」「自分には関係のないことだ」と感じています。
虐待は特別な家庭で起こるもので、自分の周りには存在しない。そうした考え方は、無意識のうちに他人事としてこの問題から距離を置くことにつながっています。
だからこそ、今一度、考えてみませんか?
児童虐待は、家の中や、親子間だけの問題と思っていませんか?
例えば、学校の先生、保育士、スポーツコーチ、クラブ指導者、ベビーシッター、親戚の人、親の友だち、近所の人など、子どもに関わる職種や日常的に身近にいる存在(第三者)が、「虐待者」となる場合があります。
この場合、子どもから信頼を得ていたり、巧妙な「てなずけ」によって虐待と意識させなかったりするため、被害が潜在化しやすいです。
また、世界的に見ると、性搾取を目的とした児童誘拐や人身売買といった犯罪も深刻であり、この危険性(子どもを狙う魔の手)は、現代の子どもたちが簡単にアクセスができるオンラインゲームやSNSなど、インターネットの中にも多く潜んでいます。
そういった子どもたちを取り巻く、あらゆる危険性について学び、子どもたち自身が「けして被害者にはならない」という意識を持ち、いざという時に自分を守るスキルを身につけておくことが肝心です。

子どもは、常に大人が守ってあげなければならない「弱者」ですか?
もちろん、子どもは大人が守るべき「弱者」です。しかしながら、大人が四六時中、子どもを見張っていることなど到底できません。だからこそ、子ども自身が「強さ」と「知識」を身につけていてほしいのです。
子どもには、本来、生まれ持った「危機管理能力」があります。
その力を、引き上げてあげることで、子ども自身で、虐待から自分の身を守ることができます。
子どもの能力を信頼してあげましょう。しかしながら、その信頼には、事前の「教え」が必要なのです。

虐待を受けている子どもの特性を、ご存知ですか?
虐待を受けている子どもは---、
- 自分に起こっていることが何なのか、分かっていないかもしれません。
- 酷い目にあうのは、自分のせいだと思い込んでいるかもしれません。
- 嘘をつかれたり、脅されたりして、何も言えないのかもしれません。
- どこに助けを求めたらいいのか、誰に話せばいいのか分からず、我慢をしているかもしれません。
だからこそ、どんな子どもにも、SOSの出し方を教えてあげましょう。
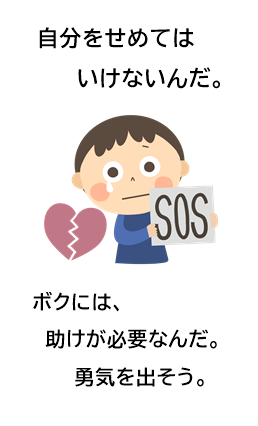
「幼児にも、性教育を」という、現代の動きをどう思いますか?
日本には、アメリカでおこなわれているような、しっかりとした児童虐待予防教育プログラムがありません。ですから、識者と言われる人たちの間では「児童への性暴力を防ぐために、幼児期から性教育をおこなおう」という認識になっています。
でも…、「性教育」というのは、違和感がありませんか?
もともと性教育は、未成年の妊娠や性病の予防に焦点を当てたものです。 虐待予防と一緒にしてしまうと、焦点がぼやけてしまいます。性暴力は「犯罪」です。その意識を持ち、「自分は被害者にならない」という強い意志を育むことが重要なのです。

いまだ多い「必要なし」の声を、どう思いますか?
ある行政職員から、このように言われました。
「普通に幸せに育っている子どもたちに、わざわざ虐待について教える必要がありますか? 子どもたちを怖がらせるだけではありませんか?」
あなたは、この言葉に賛成ですか?
今や、現代社会は「複雑怪奇」と言っていいほどに複雑で、犯罪がうごめきあっています。そのなかで、幸せに育っている無垢で無知な子どもたちこそが、虐待者や犯罪者にとって「格好の獲物」なのです。
「無知」は、とても危険です。
だからこそ、危険を知り、対処の仕方を知り、予防の仕方を知る必要があるのです。

四つの『育』へのアプローチ
児童虐待予防教育は、単に虐待の事実を伝えるだけでなく、子どもの育成に不可欠とされる四つの「育」、すなわち「知育」「食育」「徳育」「体育」に深く働きかけ、健やかな成長を多角的にサポートします。
アプローチする、四つの『育』

①「知育」への働きかけ
子ども自身が「自分の安全を守る権利」を理解し、不審な状況や危険な兆候に気づく力を育みます。
②「食育」への働きかけ
食事はただお腹を満たすだけではなく、生命と健康を支える最も基本的な部分であること、また、家族との団らんや温かい交流の時間でもあり、子どもにとって「心の栄養」にもなります。
規則正しい食事の大切さや、栄養バランスのとれた食事が不可欠であることを伝え、また、食べることの楽しさを教えることにより、「育児放棄」の早期発見、早期改善につなげることができます。
③「徳育」への働きかけ
徳育は、他者への共感や信頼を育む上で重要な要素です。自己肯定感を高めるとともに、他者の痛みや感情を理解する力を養います。自分を大切にすること、そして他者を尊重することを学ぶことで、子どもは健全な人間関係を築くための基礎を固めることができます。
④「体育」への働きかけ
体育は、単に体を動かしたり、スポーツを楽しんだりするだけでなく、心身の健康を維持することを目的とします。この「心身の健康の維持」という考え方は、虐待予防の観点から「自分自身を守る」という重要な概念でもあります。体育は、自分を守るために必要な、身体的な側面での具体的な行動と、心理的な側面での強い意志を育むことができます。
このように、児童虐待予防教育は、知育、食育、徳育、体育という四つの「育」を包括的に支え、子どもの可能性を最大限に引き出します。この教育が社会に広く浸透することで、子どもたちが安心して成長できる、より良い未来を築くことができるでしょう。
児童虐待予防教育は、
世界中で必要とされています。

